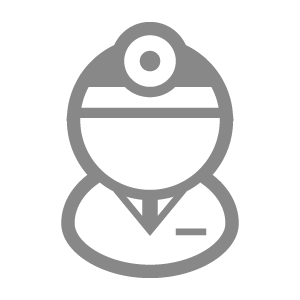
- ACP(アドバンス・ケア・プランニング)について
- 投稿者:しらさぎ苑 栁 大三郎
──黄色いファイルが教えてくれたこと──
「実家の父の本棚にこんなものがありました」と、黄色いプラスチックのファイルを手に面会に訪れたのは、施設入所中のAさん(戦争体験のある方)の長女でした。Aさんは工業高校で建築を学び、ご自宅の設計から有名な建造物にも関わるなど、幅広く活躍された方でした。
ここ1年ほどは食事量や活動意欲が落ち、日中も寝て過ごす時間が多くなっていたため、ご家族と今後のことを話し合うべき時期と判断し、遠方から施設にお越しいただくことになりました。
娘さんが取り出したそのファイルは、Aさんご本人が10年前に作成したもので、表紙には「老後の計画書」と記されていました。内容には、「実家の後始末に関すること」や「こんな施設に入所したい」といった希望に加え、「無理な延命は望まない」「痛みや苦しみは避けたい」「胃瘻・心臓マッサージはしない」といった、これから私たちが話し合おうとしていた内容が、驚くほど具体的に記されていたのです。直筆の署名と捺印も添えられていました。
現在のAさんはその文書を自分で書いたことは覚えているものの、当時と考えが変わっていないかを確認するのは難しい状況です。それでも、こうした意思表示があることで、ご家族も私たち職員も方向性を共有し、落ち着いた話し合いが可能となりました。
終末期が近づく方々の思いや希望を、日頃から丁寧に汲み取っておくことが、いざというときに慌てず、ご本人にとってもご家族にとっても悔いのない選択を支えることにつながります。
このような取り組みは、現在「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」、または日本独自の呼び名として「人生会議」として全国的にも推進されています。ACPとは、将来、本人が自分で意思決定をすることが難しくなった場合に備えて、ご本人・ご家族・医療や介護の専門職が、医療やケアに関する希望や価値観を事前に話し合い、共有しておくプロセスのことです。
欧米諸国ではすでに20年以上前からこのACPが普及しており、「元気なうちに人生の最終段階をどう迎えたいか」を日常的に話し合う文化が根付いています。これにより、いざというときにも、本人の意思が尊重される医療が可能となっているのです。
一方、日本では「死を話題にするのは縁起でもない」「まだ元気なのに話すのは早いのでは」といった空気が根強く、準備の大切さは分かっていても後回しにされがちです。
ここで大切なのは、人生会議の場で「何かを決めること」が目的ではない、という点です。むしろ、「自分はどう生きたいか」を話し合うプロセスそのものに意味があります。正解を出す場ではなく、気持ちを伝え合う場なのです。
「人生の最終段階を考えるなんて、暗い気持ちになるのでは」と思われる方もいるかもしれません。しかし、それは生きている今日をより大切に、悔いなく生きるためのきっかけにもなるかもしれません。
「自分は5年後、10年後、どんな暮らしをしていたいか」「そのとき、どんな治療を受けたいか、何を望まないか」――そうしたことを少しずつ言葉にしておくことは、自分の尊厳を守る力になると同時に、残されたご家族への最大の思いやりにもなります。
この地域で言えば、島田昇二郎先生の講演を聞かれた方もたくさんおられると思いますそして「もしもノート」という小冊子も配布しており、関心のある方は医師会までお問い合わせいただけます。こうした取り組みが少しずつ広がってきています。
あの黄色いファイルが私たちに教えてくれたのは、
「“その時”に備えることは、最後まで自分の尊厳を守ること、そして残された方への思いやりである」ということでした。
※今回病気の話題ではありませんが、皆さまの健康と人生にとって大切な“備え”についてお伝えしました。
令和7年8月

